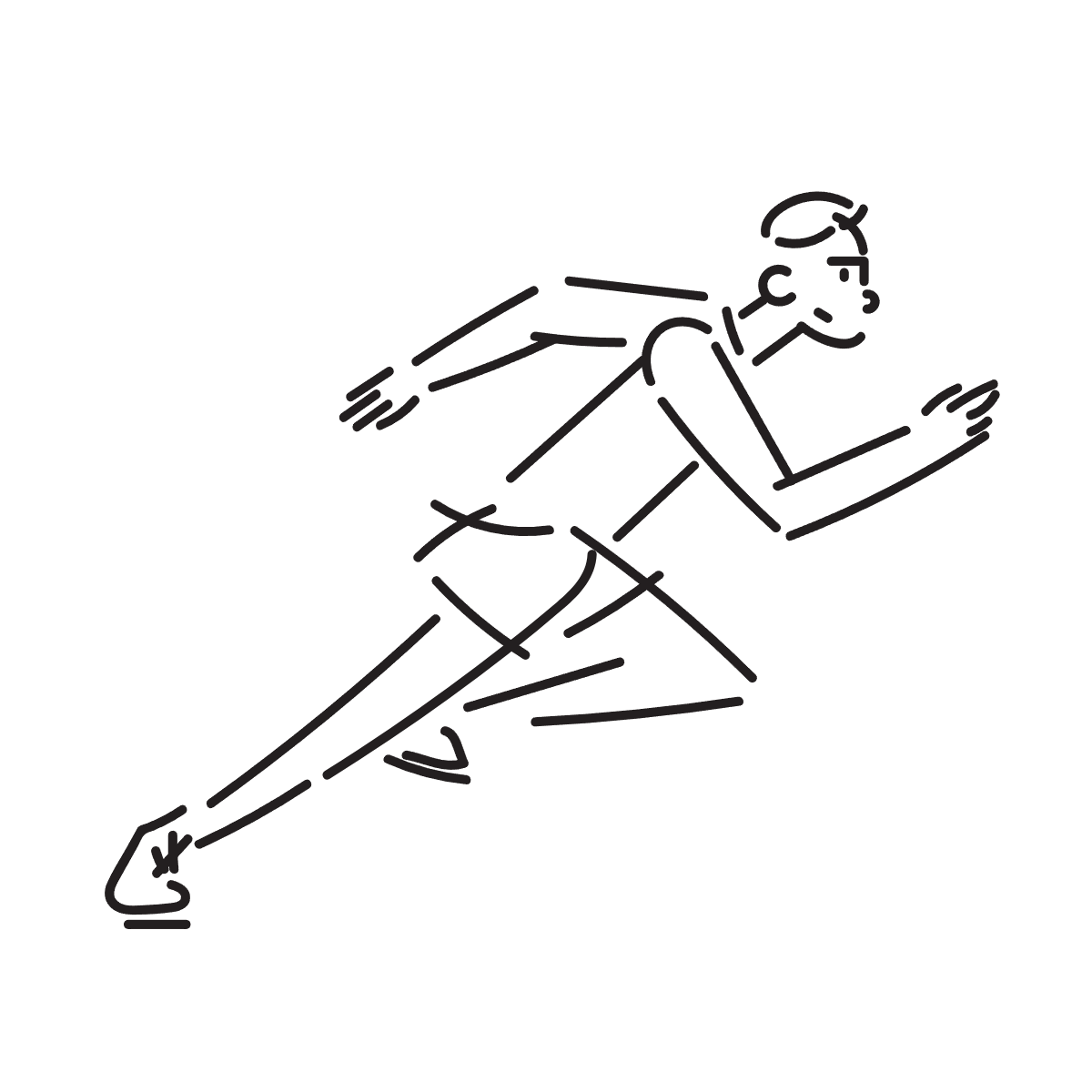製造業の現場では、発注業者を1社に絞ることのリスクが、ここ数年で大きく注目されています。特に、パンデミックや地政学的リスクによる供給網の寸断が現実となり、多くの企業が生産停止や納期遅延に追い込まれたケースを目の当たりにしました。こうした問題を未然に防ぐためには、発注先を分散する戦略が欠かせません。
発注先を増やすことのメリット
- 供給リスクの低減 発注先を複数持つことで、1社が供給不能になっても他の業者でカバーできる体制が整います。
-
例: 特定の地域に集中しているメーカーが自然災害で被災した場合、他地域の業者がバックアップとして機能。
-
価格競争の促進 複数の業者と取引することで、価格交渉力が強化されます。また、市場価格に近い透明性のある取引が可能です。
-
例: 「外観検査」のための機械を導入した某企業では、2社以上の提案を比較することで、最適なコストパフォーマンスを実現。
-
技術革新への対応 各業者が提供する技術やサービスの幅が広がるため、最新技術を取り入れる選択肢が増えます。
業者分散の成功に向けた具体策
1. リスク分析を徹底する
まずは現在の発注先が抱えるリスクを可視化しましょう。 - 地理的リスク(自然災害、輸送距離など) - 財務リスク(業者の経済状況)
2. 発注先の評価基準を明確に
「品質」「コスト」「納期」「技術力」などの基準を設定し、候補業者をスコアリングします。これにより、現場のニーズに最も適した業者を選定しやすくなります。
3. トライアル発注を活用する
いきなり大口発注を行うのではなく、小規模なトライアル発注から始め、実際の品質や対応力を確認することが重要です。
4. 契約書でバックアップルールを整備
サプライチェーンの混乱時にどの業者がどの程度まで対応できるのかを明文化しておくことで、いざという時の混乱を防げます。
現場での実践事例
ある電子部品を製造する企業では、主要な部材を3社から調達する体制を整えています。通常時は最もコストパフォーマンスの良い業者に70%を発注し、残り30%を他の2社に分散。これにより、主要業者が想定外の供給停止に陥った際も、生産ラインを止めずに対応しています。この戦略は、リスク管理とコスト削減を両立した理想的なモデルといえます。
今後の展望:DXとの連携
デジタル技術の進展により、発注先の分散管理も効率化が進んでいます。製造業向けの「サプライチェーン管理システム」を活用することで、各発注先の納期、品質、価格をリアルタイムでモニタリング可能です。これにより、より精緻な発注計画が立てられるだけでなく、トラブル時の迅速な対応も実現できます。
発注先を単一に依存する時代は終わりつつあります。多様なリスクに備え、発注先分散の戦略を取り入れることで、製造業の安定的な成長が見込まれるでしょう。