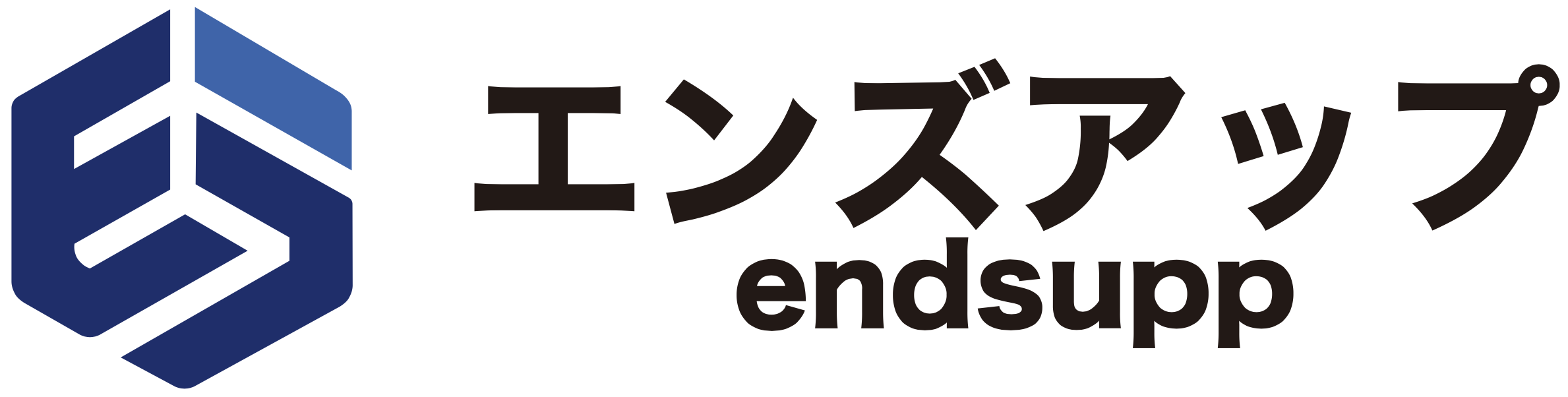止まらないラインは“最悪”?─その理由とは
一見理想に見える「ずっと止まらないライン」。しかし、それは現場が持つ本当の課題を隠してしまっているかもしれません。
ある製造企業では、「止まらない=改善が進んでいない」と定義し、ラインを意図的に“止める”設計を行っています。なぜなら、ライン停止が改善のヒントを与えてくれるからです。
ラインが止まるたび、現場が学ぶ──改善型生産の実例
✅ ストップが起点になる改善サイクル
- 作業者が異常を感じたら、即座にスイッチでコンベヤーを一次停止
- 赤いランプとアラームで、どこで・なぜ止まったのかを即時に共有
- 管理者が現場に駆けつけ、原因を確認して再発防止策をその場で議論
この仕組みによって、単なる“対処”ではなく、改善活動の発見ポイントとしてストップを活用しています。
データが教えてくれる「改善すべき工程」
ラインの停止情報はすべて記録されます。
- どの工程で
- 何が原因で
- いつ、どのくらいの時間止まったのか
これらの情報をもとに、毎日反省会議を実施し、次の改善につなげるPDCAが現場単位で回っています。
あえて“無理”をかけることで、弱点が見えてくる
この企業では、生産目標に対してあえて厳しめのタクトタイムを設定します。
- 例えば、本来60秒かかる作業を、56秒で行うように設定
- 少し無理をかけることで、“どこがついていけないのか”が可視化される
- 止まった場所が「改善すべき場所」であり、優先順位が明確になる
この「ストップから始まる改善」は、止まらないことをゴールとせず、止まりながら成長していくスタイルです。
工程ごとに“1つの工場”として考える
この現場では、「1ライン=1工場」という考え方を取り入れています。
- 各工程が独立してQ(品質)・C(コスト)・D(納期)を意識
- 多品種少量生産にも柔軟に対応
- 小さな改善を繰り返し、各ラインが自律的に進化
この姿勢が、高い品質と効率を維持した“Made in Japan”を支えています。
人とロボットの“ちょうどいい協調”がカギ
この生産現場では、自動化も積極的に取り入れています。
- 小型部品の取り付け作業に協調ロボットを導入
- 高頻度の組立作業はロボットによる全自動化
- 工場内搬送はAGV(自動搬送車)によって完全無人化
ただし、すべてを機械任せにはしていません。“人とロボットが得意なことを分担する”ライン設計が重視されています。
まとめ:止まることで見えてくる、本当の改善
- 止まらない=最適とは限らない
- 止まった理由こそが、次の改善のヒント
- “無理”をかけて見える“ムリ・ムダ・ムラ”を改善に変える
今後、生産現場に求められるのは「安定」だけでなく、「変化を受け入れて進化する力」です。
止まることを恐れず、“止まりながら進む”改善の現場づくりが、これからのスマート工場の土台となっていくでしょう。
📌